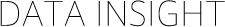両親が授けてくれたもの

米良はるか(めら・はるか) Readyfor株式会社代表取締役CEO。1987年、東京生まれ。2010年、慶應義塾大学経済学部卒業。2012年、同大大学院メディアデザイン研究科修士課程修了。大学在学中に東京大学と産学連携ベンチャーにて「あのひと検索SPYSEE」の立ち上げに関わり、その後、スタンフォード大学でクラウドファンディングについて学ぶ。大学院在学中の2011年、ウェブベンチャー・オーマ株式会社の一事業として日本初のクラウドファンディングサービス「Readyfor」を設立。2014年7月に株式会社化し現職に就く。2012年には世界経済フォーラムグローバルシェイパーズ2011に選出され、スイスで開催されたダボス会議に日本人として最年少で出席。内閣府「国・行政のあり方に関する懇談会」の委員を務めるほか、国内外の多数の会議に参加している。
祖父は発明家、父はコピーライターという家庭で、私は幼いころからクリエイティブなことを身近に感じて育ちました。特に父は、私が人生で最も影響を受けた人といっても過言ではありません。
父は資生堂にコピーライターとして20年ほど勤めていました。目の前にあるものにとどまらず、社会全体をクリエイティブの力で変えていきたいという思いが強い人で、独立後は自分で事業を興し、マルチパラレルキャリアを実践していました。そうした父の考え方は、ひとり娘の私に対する教育方針にも通じていたように思います。いわゆる女性としての幸せを得るための道を用意するというのではなく、ひとりの人間として社会に役立つことを自ら考え、選んで生きていけるような環境を与えてくれたのかな、と。だから私が自分で選択したことには絶対にダメとは言わず、何でも心から応援してくれました。
母は富山の出身で、高校を卒業後、父と同じ資生堂に入社し、地元で販売員をしていました。社交性が非常に高い人で、売り上げ成績も抜群によかったそうです。そのころ資生堂が海外で販売員を募集するという制度があったらしく、母は英語も全然しゃべれない、海外どころか東京にもほとんど行ったことがないにもかかわらず、単身で富山からいきなりニューヨークへ。治安が悪い中、人種差別も受けながら、持ち前の社交性と無知であることをいい意味で利用し、数年間がんばったようです。帰国後は東京で資生堂の広報室に勤務。そこで父と出会い、私が生まれるときに仕事を辞めました。ずいぶん悩んだそうですが、高卒でキャリアアップしている人が誰もいない環境だったため、出産後も働き続けてキャリアを設計していくことは難しかったのでしょう。
父と母の教育方針は、最終的に自分で選択ができる人生を歩ませたいという点では同じだったと思います。ただ、父が私を自分で物事を考えて判断できる人間にしたいと思っていたのに対し、母は自分が叶えられなかったキャリアをつくってあげたいという思いが強かった。娘を大企業で働くキャリアウーマンにする将来像を描いていたので、私が起業の道を選んだときは反対され大げんかしました。でもいまは、私がこうしてメディアや様々な場で意見を言わせていただいているのを見て、社会に評価される対象になるような仕事なんだということは何となく理解しているようで、母親として何かにつけサポートしてくれます。ありがたいですね。
ネットの可能性に魅せられて
私が小学校から高校まで通っていた成城学園は、幼稚園から大学・大学院までの一貫校で、ユニークで自由な校風でした。小学校は遊びが8割、勉強が2割みたいな感じで、クラスのみんなで脚本や曲をつくってミュージカルを上演したりするような、何かを創り出すことに真剣に取り組む学校でした。いま思えばいい影響をたくさん受けたと思います。
その成城学園を高校で出て慶應義塾大学に行ったのは、中学のころの家庭教師の先生がきっかけでした。その先生は幼稚舎から慶應で、当時、経済学部の藤田康範ゼミ(※1)に所属していたんですが、私がそれまでに出会った誰よりも楽しそうに大学の話をするんです。成城よりも楽しい学校があるのかと思ったら、どうしても行きたくなって、私も経済学部を受験して藤田ゼミに入りました。
東京大学の松尾豊先生(※2)と出会ったのも藤田先生の紹介でした。藤田ゼミは企業やほかの研究室と様々なコラボレーションに取り組んでいて、その中のひとつが松尾研究室との共同研究だったんです。そこで「あのひと検索SPYSEE(以下SPYSEE)」(※3)の開発プロジェクトに携わりました。そのころ私は大学3年生で、卒業後の進路について考えてはいましたが、稼ぐために働くということが全然ピンと来なくて、やりたいことも何もありませんでした。そんなときに、松尾先生のもとでアイデアがどんどん実現していくインターネットやテクノロジーの面白さを知り、無限の可能性を感じました。そして、新しい世界をつくっていくことに自分の力を尽くして世の中の役に立ちたいと思うようになったんです。
SPYSEEは人物プロフィールと相関図がわかる検索システムで、当時すでに80万人分の個人データがありました。こうした個人の情報が自動的にどんどん紐づいていけば、これからはいままでのように企業や組織ではなく、その中で活躍している優秀な“個人”が際立つ社会になっていくに違いない。そうした才能ある人や、成し遂げたいことがある人を応援するサイトをつくれないかと思い、松尾先生に相談して立ち上げたのが、個人で寄付できるサービス「あのひと応援チアスパ!」(cheering SPYSEE、以下チアスパ)です。そこでパラリンピックのクロスカントリースキー日本代表チームのワックス代100万円の寄付を募ったところ、目標額を超える資金が集まりました。特殊な能力があるわけでもない自分のような人間でも、行動を起こして気持ちを伝えれば、それに反応してくれる人たちがいて、これだけのお金が動くんだということがわかり、大きな自信になりました。

大学を出たら就職することも考えましたが、インターネットについてもう少し学びたいと思い、慶應大学大学院のメディアデザイン研究科に進みました。大学院に入ってからも松尾先生の研究室にはしょっちゅう出入りしていたので、先生がゼミ生を連れてアメリカの学会に行くことになったとき、私も同行させてもらったんです。学会の後、シリコンバレーを回り、GoogleやFacebookなどいろいろなITベンチャー企業に連れていってもらい、生まれて初めて起業家という人たちに会って話をしました。それはとても刺激的な体験で、世界でナンバーワンになるために自分の領域を決めてストイックに取り組み、年齢も国籍も関係なく、アウトプットで勝負している。こんな世界があるのかと、感動するほど影響を受けました。これは日本にいる場合じゃないと思い、帰国するとすぐに留学手続きを始め、IT起業家がたくさんいるスタンフォード大学に留学したんです。
スタンフォードでは、プログラミングとテクノロジーアントレプレナーシップという起業家論の授業を受け、インターネットやビジネスについて学びました。チアスパの経験から自分のやりたいことは明確になっていましたが、こういう仕組みをクラウドファンディングと呼ぶのだということは、その過程で初めて知りました。アメリカでは、その前年くらいからクラウドファンディングが起こり始めていて、当時、全世界で200ほどのサイトが立ち上げられていました。私も帰国すると、早速、松尾先生の研究所で新しいクラウドファンディングの構築に取りかかりました。それが「Readyfor」(※4)です。
Readyforの原型であるチアスパは、一定の成果を挙げることはできましたが、私はこのままではいけないと思っていました。クラウドファンディングは「寄付型」「投資型」「購入型」の3種類に分類することができ、チアスパはこの内の寄付型でした。寄付というのは一時的なもので、せっかく賛同してお金を出しても、そのお金がどう使われたのか、本当にちゃんと届いたのかどうかさえわからない。それでは誰かを応援しているという実感が持てないと思うんです。支援を受ける人だけでなく、支援する人にも満足してもらえるようにするには、ちゃんとレスポンスが得られるコミュニケーションが必要だと感じました。
そこでReadyforは、支援してくれた人に金銭以外の物品や権利でお返しをする「購入型」を採用。「資金を出していただいたおかげで出来ました」という感謝の気持ちとともに、その一部が戻ってくる仕組みにしたのです。購入型なら金融商品取引法の規制を受けないこともわかり、いよいよスタートというとき、現在競合になったある企業が同じタイミングでクラウドファンディングを始めることを知りました。その企業の代表はすでに知名度のある人でしたが、私はまったくの無名。でも私は超がつくほど負けず嫌いで、競争が大好きなので、イニシアチブを取るための戦略を考えたんです。それは、クラウドファンディングについて誰よりも詳しい人になり、この分野の権威になること。すぐに論文をまとめて学会に提出しました。その結果、色々な人が私に話を聞きに来るようになり、回答することによって自分たちのサービスも宣伝できるというループをつくることに成功しました。
応用経済理論・経済政策を専門とする、慶應義塾大学経済学部の藤田康範教授が主催するゼミ。産学協同プロジェクトをはじめとするイノベーティブな授業内容で人気が高く、高倍率の入ゼミ試験に合格した学生だけが受講できる。
東京大学大学院工学系研究科の特任准教授。人工知能とウェブ工学を専門とし、国内外に数々の論文を発表。ビッグデータ分析を中心に企業との共同研究も行う。2014年より人工知能学会倫理委員会委員長。人工知能学会2016年度全国大会優秀賞受賞。
オーマ株式会社が運営する、人に関する事柄を調べることを目的とした検索エンジン。あらゆる人物の情報をウェブ上から集めてプロフィールを紹介し、その情報からつながりの強い人のネットワークを生成した相関図や、タグ、キーワードなどを表示する。
日本初、国内最大のクラウドファンディングサービス。「実行者」と呼ばれる企画者が、申請・審査を経てサイト上にページを作成・公開。不特定多数の「支援者」に出資を求める。通常は数ヶ月先の終了期間までに目標金額を超えればプロジェクトは成立。Readyforでは、貧困問題、環境問題、災害支援、地域活性化、医療・福祉など、社会貢献型の企画が多い。社是は「誰もがやりたいことを実現できる世の中をつくる」。
ダボス会議に参加して
Readyforの始動から1年ほど経ち、大学院修了を目前に控えたころ、ダボス会議(※1)に参加するという好運に恵まれました。そこでエリック・シュミットやショーン・パーカー(※2)がインターネットを活用した慈善活動というテーマでセッションをしていて、メイントピックがクラウドファンディングだったんです。その話を聞き、ちょうどこの道を進んでいいのかどうか迷っていた時期だったので、自分がしてきたことは正しいと言ってもらった気がして勇気づけられました。また、20代の若者が70人くらいいたんですが、何者にもなれる可能性を持った人たちと、過去の歴史や国境も超えてつながっていることに、楽しさや心強さを感じる一方で、刺激もたくさん受けました。レアな人生を歩むと、その分チャンスがたくさん巡ってくる。だからこういう場に参加することもできたわけですし、この選択をしてよかったとあらためて感じました。
Readyforは、松尾先生が代表を務めていたベンチャー企業「オーマ株式会社」の一事業としてスタートし、2014年にスピンオフする形で株式会社化しました。もともと「資金がなくてもみんなに協力してもらいながら、誰もがやりたいことを実現できる世の中をつくりたい」という思いから始めたことなので、会社経営に興味はありませんでしたが、自分を奮い立たせるために株式会社にする道を選びました。現在、正社員は約60人。インターンや業務委託も含めて70~80人のチームで運営しています。
2011年のサービス開始から6年間で実施したプロジェクト数は約7000件。達成率は7割ほどです。最近で印象に残っているのは、東京世田谷の国立成育医療研究センターのプロジェクト。小児がんや免疫不全の治療に必要な無菌室をつくるための資金を募り、メディアを集めて記者会見したところ、目標金額は1500万円だったんですが、瞬く間に2000万円集まり、最終的には3000万円を超える資金が集まりました。自分の子供が昔無菌室で治療してもらったという人や、いままさに無菌室にいますという人、たくさんの方が闘病中の子供たちへの励ましのコメントともにお金を出して下さいました。いままでは応援したいという思いがあっても、仕組みが可視化されていなかったので、そこに対して行動を起こすことに抵抗があったと思います。でもいまはネットでコミュニティがつながっていますし、内容もカテゴライズされているので、応援してほしい人と応援したい人、響き合う人同士をうまくマッチングさせてつなぐことによって、必要なところにちゃんとお金を届けることができる。それを実感した事例でした。
スイスの経済学者、クラウス・シュワブの提唱により1971年に発足した、世界経済フォーラム(WEF)が毎年冬にスイスのダボスで開催する年次総会。世界各国の政財界のリーダーや学者など選ばれた知識人が3000人以上集まり、世界経済について対等に話し合う。日本からは2001年に森喜朗首相(当時)が現職の首相として初めて出席して以来、歴代内閣総理大臣の多くが出席している。
エリック・シュミットはアメリカの経営者、プログラマー。グーグルの持株会社アルファベットの会長。2001年から2011年までグーグルのCEOを務めた。/ショーン・パーカーはアメリカの起業家。ナップスター、Plaxo、Causesの共同設立を経て、フェイスブック初代CEOを務めた。
お金が回っていく社会をつくりたい
振り返ると、ここまでノンストップで走ってきた気がします。生半可な取り組みではインフラにできないと思ったので、競争意識を持ち、常にナンバーワンであることを目指して取り組んできました。最初から一貫していたのは、クラウドファンディングの仕組みを、自分が提唱者(アドボケーター)の位置づけで広げていこうということ。夢の実現に向けて一歩踏み出すきっかけを与えてくれるツールだと信じていたので、多くの人に知ってもらいたいという思いだけでここまでやってきました。ただ、クラウドファンディングはいままでにない新しいお金の使い方なので、一度でも使ったことがある人は「すごくおもしろい」と言ってくれますが、「1回やってみる」ことのハードルはまだ高いのかなという気がします。今後はそこが課題ですね。
私は、お金を儲けることには興味がないんです。ただ、お金がうまく回っていく社会をつくりたい。お金が一部のところに滞留して格差が広がった状態は、人々の不平等感を生み、社会を不安定にさせる要因になるので、それが続けば世界は必ず戦争へ向かって荒れていくでしょう。せっかくこんなに平和な時代に生まれたのだから、その問題を解決する仕組みをつくることによって、できる限り平和な時代を持続させたい。それがこの時代に生きている人間の使命だと思っています。そのためにもReadyforは、資本や資産の有無にかかわらず、誰もがやりたいことにチャレンジできる万人に開かれた場でありたい。そしてこのサービスがもっとうまく回っていくよう創意工夫し、少しでも世の中に寄与していきたいと思っています。

※この記事は、当社広報誌『INFORIUM』第8号(2017年11月30日発行)に掲載されたものです。