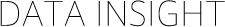1.なぜ今、脳科学なのか
「脳」というキーワードが連日のようにメディアを賑(にぎ)わせ、脳の秘密についての解説本や脳をトレーニングするためのゲームなどが相次いで登場しており、脳科学に対する社会や消費者の関心・興味の高さが伺えます。このように脳科学が広く注目されるようになったのは、身体に影響を及ぼすことなく脳の「見える化」を実現する非侵襲型の可視化技術が飛躍的に発達し、脳の状態を容易に計測できるようになったことが背景にあります。代表的な技術として、例えば次の3つが挙げられます。
代表的な脳の可視化技術
- 1.f MRI(機能的磁気共鳴画像法)
病院などで使用されているMRIを利用して、脳の血流動態反応を画像化し脳の活動部位や変化を捉える技術。東北福祉大学特任教授(当時米国ベル研究所)の小川誠二先生による開発。
- 2.NIRS(近赤外線機能画像法)
近赤外線を頭皮に照射し、脳活動に伴って生じる脳内のヘモグロビンの増減により変化する反射光を頭皮上で計測する技術。日本発の技術とも言われており、日本メーカーによる開発が進んでいる。
- 3.EEG(脳波)
脳活動に伴って頭皮上に発生する数十マイクロボルト程度の電位変化をセンサーで計測する技術。旧来から、てんかんなどの臨床検査や治療に利用されていたが、デジタル技術の進歩に伴い、画像解析装置としてさまざまな脳研究分野で活用されている。
日本が世界をリードする「脳の可視化」技術によって脳科学研究は急速な発展を遂げつつあります。私たちの行動におけるさまざまな脳の働きが解明され、認知・行動・記憶・思考・情動・意思といった人間の「心」の働きに関する知見が蓄積されてきました。それらの知見を核として、経済学・社会学・生理学など多岐にわたる研究領域と融合した応用脳科学研究が進展。その結果、医療・福祉分野だけでなく、経済分野や産業分野における事業活用への取り組みも活発化しています。ニューロエコノミクス、ニューロポリティクス、ニューロマーケティング、ニューロマネジメントといった言葉も生まれてきました。
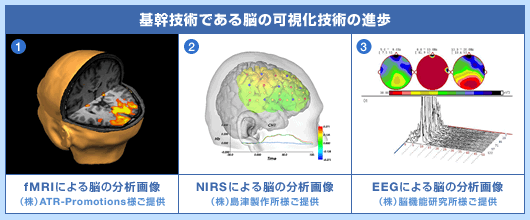
図1:代表的な非侵襲型の脳の可視化技術
2.グローバルに推進される脳科学研究
経済分野や産業分野などにおいて、脳計測技術を利用した脳研究は今や世界中で行われています。ここでは、グローバルな動向と日本の状況について概観します。
国を挙げてビジネス化へ積極的に挑む欧米・アジア
米国では国が中心となって、1990年ごろから脳科学研究に積極的に取り組んでおり、近年では人間の心や行動と脳の関係に関する科学的な理解を促進することにも注力しています。多くの有名大学には脳科学研究に特化した神経科学部も創設され、大学周辺にはニューロベンチャーが林立しています。研究者の数は日本の8倍、研究予算は日本の20倍ともいわれ、ガン研究やヒトゲノムの研究に匹敵する規模を持ち、基礎研究中心の日本とは大きく異なります。
また欧州では、1998年からEU主導で加盟各国が参加して「脳科学はITのために何ができるか」という基本命題のもと、「Neuro-IT」というコンセプトでライフサイエンスと情報工学を組み合わせた脳科学を推進しています。知財・人材の交流を図るとともに、基礎研究のポテンシャルを産業界・経済界に伝達することにも尽力。「Neuro-IT」に加えて、ライフサイエンスと情報通信技術の相乗効果を期待した「Bio-ICT」という新たなコンセプトも構築し、研究活動を行っています。
こうした動きはアジアでも活発です。中でも中国は神経科学の研究に極めて熱心で、BMI(Brain Machine Interface)分野では世界的に評価が上昇しつつあります。韓国では脳研究促進振興計画を立て、2017年までに脳研究(科学技術論文と特許技術)で世界第7位に入ることを目標に、2009年度には610億ウォンを投入。R&Dの中核人材1万人を育成するとともに、脳関連市場規模を3兆ウォンに拡大するための基盤を整備する方針を打ち出しています。
基礎研究で世界をリードするも、産業応用で出遅れる日本
そうした海外における状況に対して、日本では、脳を可視化するニューロイメージング技術や、医療分野を中心とした基礎研究に関しては、世界をリードする研究開発レベルにあるものの、ビジネスへの応用においては海外に比べて後れを取っているのが現状です。
そうした中、産業応用に向けた取り組みとして、2007・2008年度にNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)で「脳科学の産業分野への展開に関する調査事業」「脳科学の産業応用への推進に資する脳機能計測機器に関する調査事業」が実施されています。また、2010年から総務省が「脳とICTに関する懇談会」を設置し、チャレンジド(障がい者)や高齢者への支援、また超低消費エネルギーかつ不測の事態でも柔軟に対応できる情報通信ネットワークの実現について検討しています。ただ、脳科学の産業応用という視点から見ると必ずしも先進的とは言えません。グローバルなビジネス競争の激化に伴い、日本における脳科学の産業応用に向けた研究開発の停滞・遅延が危惧(きぐ)されています。
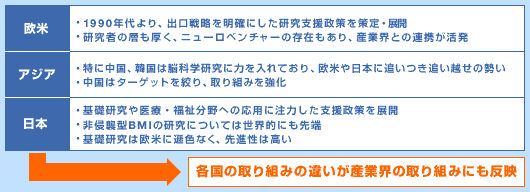
図2:各国が推進する脳科学の研究状況
3.グローバル企業における脳科学の活用状況
続いて、米国をはじめ海外における脳研究の産業分野への展開がどのように行われているかを示すいくつかの事例を紹介しましょう。
例えば3M社は、脳と視覚の関係をモデル化したVAS(Visual Attention Service)というシミュレーションシステムを、有料の顧客サービスとしてインターネットで全世界に展開しています。これは、独自に開発したデータベースとアルゴリズムを用いて、印刷物・看板・陳列棚などについて最初の数秒間に人がどこをどのように見るかについて、視認率や注視率を推測するものです。またGoogle社では、オンラインメディアの消費行動と意思決定への影響を脳科学の観点から研究するプログラムを公募、助成しています。ユニリーバ社は、紅茶が人に与える覚醒効果と鎮静効果を脳波計測で明らかにしているほか、多感覚器官に関するWebサイトやシンポジウムを単独でスポンサリングしています。そのほかにも、食品、日用品、化粧品、自動車、IT、電機・電子、サービスといった、あらゆる分野のグローバルカンパニーが何らかの形で脳科学の研究開発に取り組み、その成果をビジネスに活用し始めています。
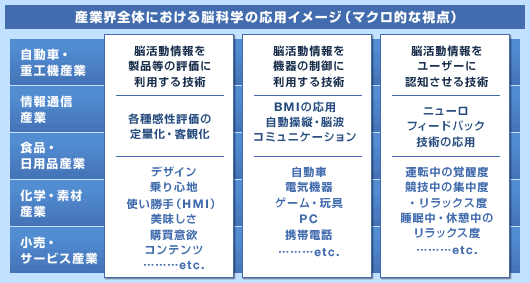
図3:産業活動における脳科学の応用可能性
4.日本企業が抱える課題と、オープンイノベーションの必要性
グローバル規模で脳科学の産業応用が進む中、日本企業で脳科学の研究開発や産業応用が進まないのは、なぜでしょうか。そこには以下の5つの大きな課題が存在します。
まず、最初にして最大の課題は、日本の企業に脳科学の専門家がほとんどいないこと。日本では脳科学を学び、研究する人の多くは基礎研究者としての道を歩み、企業も脳科学を専攻する人材を積極的に採用していないのが現状です。そうした状況が続く限り、企業が脳科学をビジネスに取り入れるのは困難と言わざるを得ません。
第2に、脳科学は異分野のエンジニアリングやテクノロジーと融合して初めて産業応用が可能となりますが、企業内にはこうした融合や複合的活用ができる人材が少ないということ。例えばロボットを動かすには、感覚器官からの情報を脳で処理して指令情報を運動系(筋肉など)に伝える脳科学的な知見と、機械制御技術やセンサー技術を融合させることが必要になります。また、ニューロマーケティングを実現するには、視覚や記憶に関する脳科学の知見とマーケティングに関するノウハウを融合させなければなりません。
3番目の課題は、脳科学がまだ新しい学問領域であり、脳科学に関する情報のキャッチアップが大変であること。脳の可視化技術の飛躍的進歩により急速に研究が進んでいるとはいえ、特に人間の心や社会性、コミュニケーションに関する研究は始まったばかりです。このような分野の情報を的確かつタイムリーに入手して社内で活用しようにも、脳科学に対する理解も進んでおらず、専門知識を有する人材などの環境や体制も整っていない状況です。
4番目は、倫理の問題です。やはり「脳」という文字がつくと、マインドコントロールされるのではないか、脳に悪影響を残すのではないかと必要以上に慎重になったり、逆に「頭の良くなる○○」のように過剰な効果を期待したりしがちです。脳科学に対する世の中の認知度が低く、企業が脳科学をビジネスに積極的に活用しづらい状況にあることも、脳科学の産業応用が進まない理由と言えるでしょう。
最後に、企業が脳科学を研究開発やマーケティングなどの企業活動にどう利用すればいいのか、そこにどんなメリットがあるのかが明確でないという、脳科学の事業関連性の課題が5番目に挙げられます。必要性を感じながらも社内に専門家がいないために、どのようにアプローチしていいか分からず、結果として他社の動向を待つという受け身の姿勢が、日本企業での脳科学の活用を遅らせています。
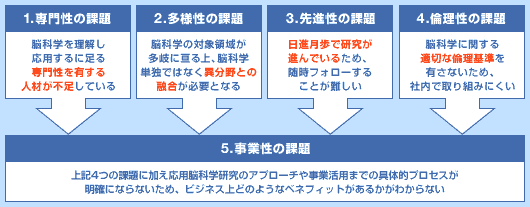
図4:日本企業が抱える脳科学を産業応用する際の課題
このように、脳科学に対する理解不足や人材不足といった課題を抱える中で、脳科学をビジネスに取り入れるためには、企業が自社内だけではなく、外部の企業や研究機関と連携して研究開発に取り組む「オープンイノベーション」の姿勢が重要であり、実際、そうした取り組みも強化され始めています。日本企業が上記の5つの課題を克服し、脳科学の積極的な産業応用に至るためには、共に協力し合って何かを創出しよう、構築しようという明確な目的や強い意志、いわば「オープンイノベーションマインド」を企業や研究機関が共有していくことが大前提であり、非常に重要となります。
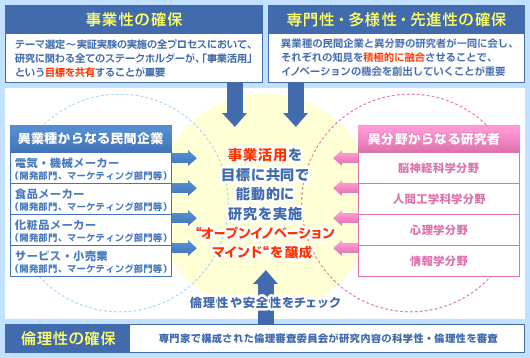
図5:5つの課題を解決するオープンイノベーションモデル
5.応用脳科学コンソーシアムが拓く脳科学の産業応用
「オープンイノベーションマインド」は、企業や研究機関によって自発的に醸成されていくことが望ましいものの、縦割り組織の社会において、日常業務で多忙を極める研究者、設計開発者、マーケティング部門や戦略・企画部門のスタッフなどにそれを求めるのは、必ずしも容易なことではありません。そこでNTTデータ経営研究所では、脳科学の産業応用を目指して、日本最大の脳科学研究者組織である日本神経科学学会や研究分野の第一線で活躍している多くの研究者の指導を仰ぎ、異分野の研究者と異業種の企業が共同で研究活動を行う場と仕組みとして、「応用脳科学コンソーシアム(CAN:Consortium for Applied Neuroscience)」を設立しました。CANは以下の3つの仕組みで構成されています。
- 1.応用脳科学R&D研究会
異業種の民間企業と異分野の研究者が、脳科学や関連領域の最新の研究知見を活用して、応用脳科学研究およびその事業活用を目指すための研究開発プラットフォーム
- 2.応用脳科学アカデミー
第一線で活躍している脳科学や関連領域の研究者を講師として招聘(しょうへい)し、事業活用という観点から脳科学を学ぶことで、応用脳科学研究およびその事業活用に貢献する人材を育成するためのプラットフォーム
- 3.応用脳科学ネットワーク
会員と研究者の交流、各種研究活動・人材育成活動に資する情報の収集、CANの活動について社会への発信などを促進するための、人材交流および意識啓発のプラットフォーム
CANには現在、20社以上の企業が参加しています。NTTデータが主催する「ヘルスケア脳情報クラウド研究会」を含め、7つのR&D研究会が立ち上がるなど、異分野の研究者や異業種企業が連携して、脳科学の事業活用を目指した取り組みを行っています。ただし、CANの活動は、最新の脳研究を商品開発に活かすための、あくまで一例に過ぎません。
脳科学を企業活動に応用する際には、「企業が実現したいテーマに合う適切な研究者の探索」、「脳科学・社会心理学・経営学などさまざまな分野の研究者と異業種企業の連携」、「企業が求めることに対する研究者側の理解と脳科学に関する企業側の知識の向上」といったことが重要になります。今後あらゆる産業活動において、脳科学を活用した知見やノウハウの集積が重要になっていくことは間違いありません。そうした蓄積は一朝一夕でできるものではなく、脳科学の進歩とともに研究成果やノウハウを丹念に積み重ねていくことが求められるでしょう。「オープンイノベーションマインド」の醸成を促しつつ、そうした企業や研究者の活動を継続的に支えることが、CANの役割であると考えています。
あらゆる企業活動の根底には、人と人との関係があります。人間の司令塔である脳をより深く知り、脳の特性を理解することが、これからの企業活動には極めて重要であり、応用脳科学があらゆる産業のコア・インフラ・テクノロジーになることは間違いないと考えています。
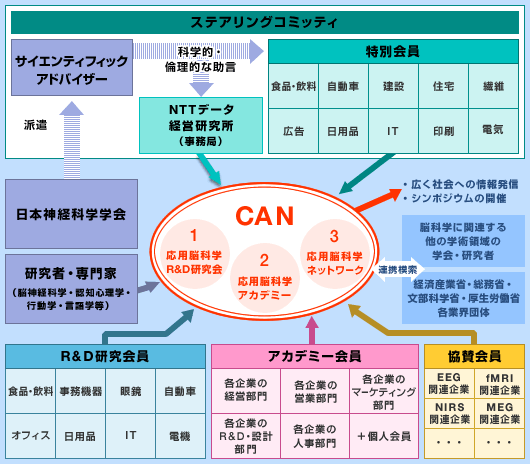
図6:応用脳科学コンソーシアム(CAN)の全体像