NTTデータのマーケティングDXメディア『デジマイズム』に掲載されていた記事から、新規事業やデジタルマーケティング、DXに携わるみなさまの課題解決のヒントになる情報を発信します。

「DX」という言葉の定義は?
まず、「DX」という言葉の定義からみてみましょう。
経済産業省の定義
日本企業のDX推進の旗振り役である経済産業省では、DXを次のとおり定義しています。
| 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、生活者や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること (「DXリテラシー標準」/経済産業省(2022年3月)) |
この定義によると、企業が「製品やサービス、ビジネスモデルを変革する」と並んで「競争上の優位性を確立すること」とされています。グローバルな競争を生き残るために、データとデジタル技術の活用によって企業文化・風土も「変革=トランスフォーメーション」するという大きな概念となっています。
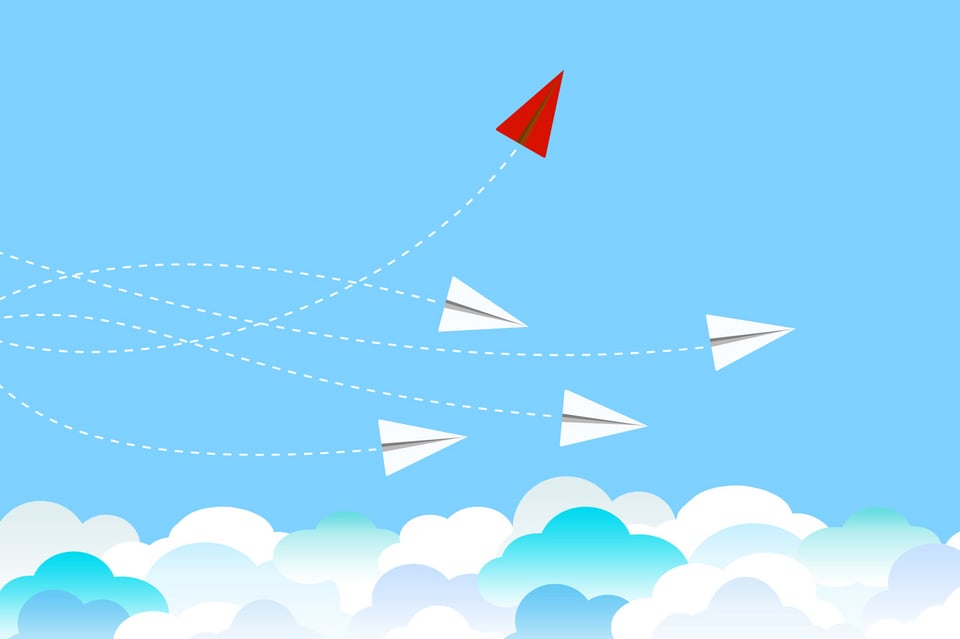
経済産業省のDXの定義
DX提唱者の定義
続いて、DXという言葉の起源もみてみましょう。
「Digital Transformation」という言葉が最初に発表されたのは2004年、スウェーデンの大学教授エリック・ストルターマン氏の論文『Information Technology and the Good Life』とされています。同氏によると、DXとは「人々の生活のあらゆる側面に、デジタル技術が引き起こしたり、影響を与える変化のこと」と定義されています。
また、この論文の中でストルターマン氏は、DXが特定のユーザーやリーダーなどを対象としたものではなく、「生活を営む人々を対象として受け止めなければならない」と強調しています。つまり、DXを語る上では、デジタル技術が「生活を営む人々」にとってよりよい「変化」をもたらすかどうかの視点が重要だということが、この定義からは示唆されます。
先ほどの経済産業省の定義をよくみると「顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革する」と、「顧客」の視点の重要性に触れています。しかしながら、DXにまつわる現在の議論の多くは、むしろ「競争上の優位性を確立する」という企業側の変革ありきの印象も感じます。

DX提唱者-スウェーデンの大学教授エリック・ストルターマン氏によるDXの定義
経済産業省やストルターマン氏の定義から紐解くDXの定義
経済産業省やストルターマン氏によるDXの定義を紹介しましたが、まだ少し抽象的な印象です。そこで、これらの定義をもう少し紐解いて「DXとは?」について考えてみたいと思います。
企業が生き残るために、デジタル技術を活用して生産性を向上させたり、組織を変革したりすることはもちろん大事です。しかし、それが何のために行われるのかがより大事と考えます。具体的には、「生活者」の視点に立ち、最良のCX(Customer Experience:生活者の体験価値)をもたらすことが、DXの出発点ではないでしょうか。
一方で、そのCXを提供するのは、企業の従業員一人ひとりです。商品やサービスを提供する従業員にとっても、デジタル技術の活用によってよい変革をもたらす、つまりEX(Employee Experience:従業員の体験価値)も重要な視点です。
以上をふまえて、DXを次のように考えてみると分かりやすいのではないでしょうか。
| DX=CX(Customer Experience:生活者の体験価値)×EX(Employee Experience:従業員の体験価値) |
デジタル技術の導入・活用によって、CXとEXを互いに高めながら相乗効果を生むことが新たな競争優位性となる。そして、その実現のために企業の組織風土・文化までもが変革される。それこそがDXの本質ではないでしょうか。

DXの本質はCXとEXを高めながら企業の組織風土・文化まで変革されること
「DX」と「デジタル化」との違いとは?
まず「DX」の定義からご説明しましたが、そもそもDXという言葉が登場する以前から、業務やサービスの「デジタル化」は企業における課題としてありました。DXは、その「デジタル化」と何がどう異なるのでしょうか?
「令和3年情報通信白書(総務省)」によると、広義の「デジタル化」に含まれる概念として他に「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」が挙げられています。
デジタイゼーション(Digitization)
既存の紙のプロセスを自動化するなど、物質的な情報をデジタル形式に変換すること
例:書類で管理していた商品の在庫数をエクセルで管理する
デジタライゼーション(Digitalization)
組織のビジネスモデル全体を一新し、クライアントやパートナーに対してサービスを提供するより良い方法を構築すること
例:商品の在庫数をシステムで管理し、在庫数が一定数まで減ったらメーカーに自動発注される
これらのデジタイゼーションやデジタライゼーションは、DXに含まれないのでしょうか?結論から言うと、経済産業省が公表している「デジタル経営改革のための評価指標(「DX推進指標」)」での定義では、それらもDXに含まれるとしています。つまり、DXの実現には、デジタイゼーションやデジタライゼーションも欠かせない要素だと考えます。

経済産業省「DX推進指標」におけるDXの範囲
なぜいまDXが重要なのか?
ここまで、DXという言葉の定義や意味を整理してきました。次に、DXが重要となってきた背景についてご説明します。
CX(顧客体験価値)の観点からの理由
「ムーアの法則」(※)のとおり、この10~20年の間にデジタル技術は指数関数的な進化を遂げてきました。その飛躍的な進化の波に乗じて、デジタル技術を起点にしたビジネスを打ち出し成長してきたのが、いわゆるGoogleやApple、Amazonなどテック・ジャイアンツと呼ばれるITメガ企業です。

DXが重要となってきた背景のひとつはCX(顧客体験価値)の観点がある
それらのITメガ企業は、単なるビジネスの領域を超えて、産業全体、ひいては人々の生活様式をも変革してきました。それを象徴する言葉のひとつに「アマゾンエフェクト(Amazon Effect)」があります。Amazonのような巨大ECプラットフォームの台頭によって、生活者の購買行動が実店舗からオンラインショッピングへと移行したことで、とりわけアメリカでは百貨店やショッピングモールが閉鎖に追い込まれるなどの大きな変化が起こっています。
デジタル技術の劇的な進化によって、今日では日々の生活にデジタル技術が浸透し、生活者一人ひとりのデジタルリテラシーが大幅に向上しました。結果、企業が提供するサービスに対しても高い利便性や顧客体験を求めるようになりました。そのように目の肥えた生活者の要求レベルに応えるために、デジタル技術を駆使してサービスを高度化し、新たな体験価値を創出しなければならない。それが、CXの観点からDXが求められている理由です。
EX(従業員体験価値)の観点からの理由
また、サービスを提供する従業員も一人ひとりが生活者であり、デジタル技術のユーザーです。従業員もまた、特に若い世代にとってはデジタル技術が生活の身近にあることに慣れています。そのような従業員が、デジタル化が十分でない自社のサービスや従業員向けの業務システムを目の当たりにすると、「こんな会社で働きたくないな」とエンゲージメントの低下を引き起こしかねません。
加えて、今日では少子高齢化によって労働力不足が常態化しており、ひと昔前の「会社が人を選ぶ時代」から「人が会社を選ぶ時代」になりつつあります。したがって、「魅力的なサービスを提供する会社で働き続けたい」「ストレスのない環境で働き続けたい」と従業員に思ってもらい、職場として選んでもらえるための環境整備が、企業にとっても重要課題となっているのです。これが、EXの観点からDXが求められる理由です。

DXが重要となってきた背景のひとつはEX(従業員体験価値)の観点がある
※「ムーアの法則」…ゴードン・ムーア氏が1965年に自身の論文で「CPUや半導体メモリなどの集積回路密度は18カ月ごとに2倍になる」と唱えた法則のこと。
9割以上の企業がDX推進に取り組めていない?
そのDXですが、日本企業における導入・推進状況はどうでしょうか。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が2020年10月に約300社の「DX推進指標」の自己診断結果を収集・分析したところ、全体の9割以上の企業がDXにまったく取り組めていない、または散発的な実施にとどまっているという結果となりました。
「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート(2020年版)」はこちら
DXを単なるレガシーシステムの刷新と捉えている企業や、DXを担うIT人材が不足していること、現状で競合優位性が保てているためDXが不要と捉えていることが、DXという言葉が大きなテーマとなっている一方で進んでいない要因と考えられます。

9割以上の企業がDX推進に取り組めていない?
DXを推進している企業の事例
DXに取り組んでいる企業のベストプラクティスは数多くあります。ここでは2つの事例をご紹介します。
<事例➀>ダイエーのレジ無し店舗「Catch&Go®」
2021年9月に、ダイエーとNTTデータが東京・豊洲のNTTデータ本社 豊洲センタービルアネックスビルにオープンした「Catch&Go®(キャッチアンドゴー)」は、レジを通すことなくキャッシュレス決済が可能な「ウォークスルー(レジ無し)店舗」です。
一般的に「無人店舗」と呼ばれる店舗においては、セルフレジのように商品を自分でスキャンするタイプの「レジあり店舗」がよくみられます。それに対してこの「Catch&Go®」は、スマホのアプリを使って入店するだけで、棚から取った商品が自動的にオンラインカートに追加され、レジ会計無しで買い物を完結することができます。
この「レジ無し」の買い物体験をしてみると、これまでのレジで並ぶことや決済する体験がどれだけストレスだったか、はじめて気づかされます。それが、この「Catch&Go®」がもたらす新たなCXです。
それだけでなく、来店した顧客の購買履歴・行動履歴をデジタルデータとして取得できます。それらのデータをもとに、顧客に最適なオファーを提案するなどのマーケティング施策が可能となり、さらに新たな顧客体験を創出することができます。
さらに、従業員の体験価値については、レジ打ちの業務から解放されること。それによって生み出された時間と労力を、より付加価値の高い業務に回すことで、従業員一人ひとりの価値向上にもつながります。
まさに、「DX=CX(生活者の体験価値)×EX(従業員の体験価値)」の典型的な事例のひとつです。

<DX推進事例>ダイエーのレジ無し店舗「Catch&Go®」
<事例②>カインズのDX戦略
ホームセンター大手のカインズもまた、「DX=CX(生活者の体験価値)×EX(従業員の体験価値)」の定義を体現する、DXのベストプラクティス企業として知られています。
同社では2018年に「IT小売企業宣言」を宣言し、2019年7月にデジタル戦略本部を設立。デジタル戦略を経営の柱の一つに位置づけ、さまざまな取り組みを進めています。
- 商品名やキーワードなどを入力すると、売り場や在庫数などが画面に表示される「Find in CAINZ」
- 「スマートフォンにアプリを導入したら200ポイントプレゼント」などの店頭キャンペーンを展開、ポイント会員からデジタル会員への移行を促進
- オウンドメディア「となりのカインズさん」の運営(サービス開始から半年で約120万PV)
また、同社の「IT小売企業宣言」では、4つある柱の一つに「メンバーへのKindness 誇りに思える、働きたい会社へ」を設けているのが大きな特徴として挙げられます。つまり、労働時間や待遇面を改善するなど、従業員の働きやすい環境を整備し「誇りに思える働きたい会社」をつくることを、デジタル戦略の土台として位置づけています。
「競争力強化」だけでDXを議論してはいけない
今、世の中の多くのDXは、「ペーパーレス化を進めなければいけない」「レガシー化したシステムを刷新しなければならない」など、主に企業側が「競争力強化のためにしなければならない」という企業目線から語られることが多いのではないでしょうか。
もちろんそれは重要ですが、DXの起点となるのはあくまで「生活者」であり、そして彼らにサービスを提供する「従業員」です。こうした生活者目線や従業員目線を欠いたままデジタル技術を導入しても、おそらく競争力強化に繋げることは難しいのではないかと考えます。
DXとは最終的に企業の文化や風土を変革することをめざすものですが、まずは商品・サービスを提供する生活者、そしてその商品・サービスを生みだす従業員が、DXの主体となります。その生活者・従業員を起点に、「私たちの企業にとってベストなCX、EXとは何か?」を考えることから始めてみてはいかがでしょうか。
監修者:小木曽 信吾

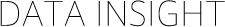

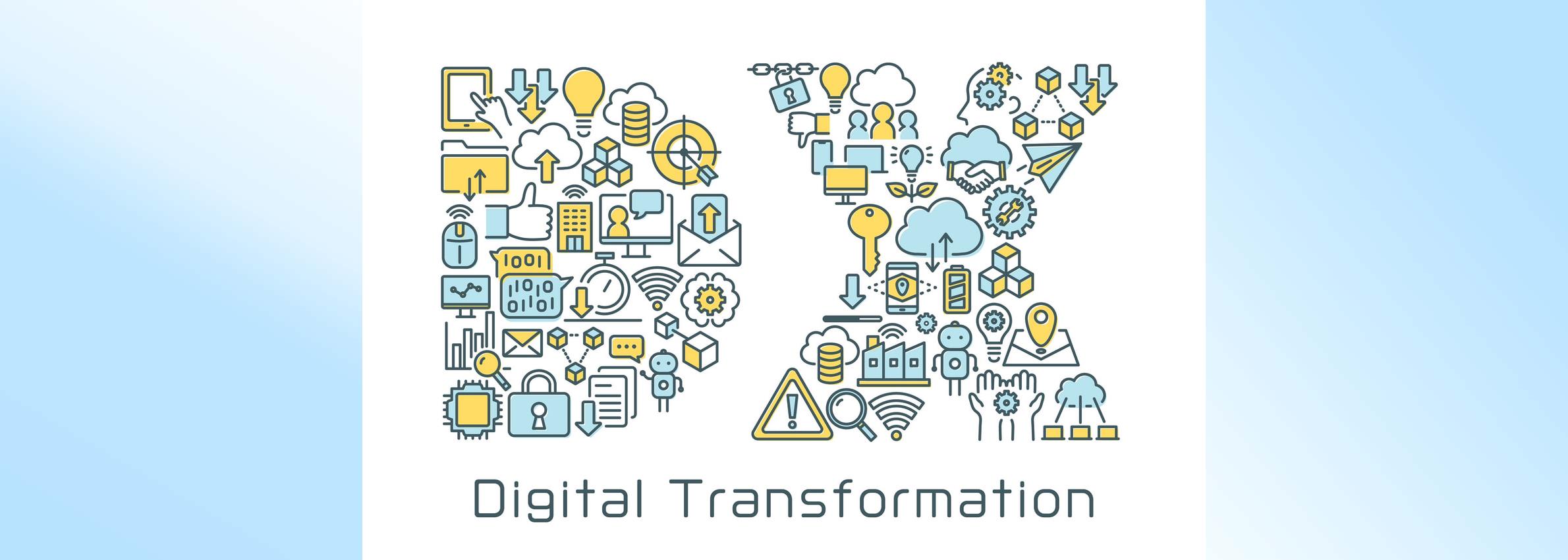

話題のウォークスルー店舗”CATCH&GO”でお買い物!筆者もビックリの購買体験とは?
https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/data-insight/2021/121390